ピロリ菌感染症とは
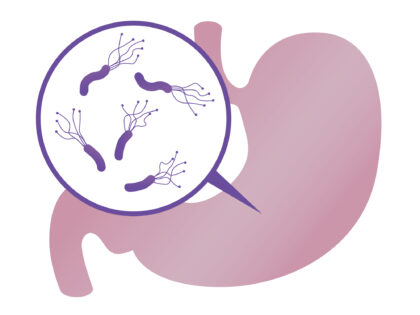 ピロリ菌は胃の粘膜に生息する細菌で、正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ」です。一般的には「ピロリ菌」と呼ばれることが多く、この菌によって引き起こされる感染症をピロリ菌感染症と言います。 ピロリ菌が胃の中に存在すると、胃・十二指腸潰瘍や萎縮性胃炎、胃がんなどの病気を引き起こすことがあります。世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関によると、世界の胃がんの約8割がピロリ菌感染に関連していると報告されています。 日本では、除菌治療の普及により若い世代の感染者は減少していますが、中高年では依然として感染率が高い傾向にあります。ピロリ菌は幼少期に井戸水や家庭内での口移しなどを通じて感染することが多く、胃がんや胃潰瘍の家族歴がある場合は、感染リスクが高まります。
ピロリ菌は胃の粘膜に生息する細菌で、正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ」です。一般的には「ピロリ菌」と呼ばれることが多く、この菌によって引き起こされる感染症をピロリ菌感染症と言います。 ピロリ菌が胃の中に存在すると、胃・十二指腸潰瘍や萎縮性胃炎、胃がんなどの病気を引き起こすことがあります。世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関によると、世界の胃がんの約8割がピロリ菌感染に関連していると報告されています。 日本では、除菌治療の普及により若い世代の感染者は減少していますが、中高年では依然として感染率が高い傾向にあります。ピロリ菌は幼少期に井戸水や家庭内での口移しなどを通じて感染することが多く、胃がんや胃潰瘍の家族歴がある場合は、感染リスクが高まります。
ピロリ菌の検査方法
ピロリ菌の感染を確認するには、いくつかの方法があります。当院では症状や年齢、健康状態に応じて最適な検査を選択しています。
胃カメラを使用しないピロリ菌検査
尿素呼気試験
息を使ってピロリ菌の有無を判定する方法で、正確かつ体への負担が少ない検査です。
血液検査(抗体検査)
ピロリ菌に対する抗体の有無を確認します。過去に感染していた場合も反応が出ることがあります。
便中抗原検査
便中のピロリ菌抗原を調べることで、現在の感染状態を確認します。
胃カメラを用いたピロリ菌検査
 胃カメラを使った検査では、胃の粘膜の一部を採取して病理検査を行い、ピロリ菌の感染を確認します。ピンポイントで組織を採取するため、まれに菌がいない部位が採取されると、感染していても「陰性」と判定されることがあります(偽陰性)。
胃カメラを使った検査では、胃の粘膜の一部を採取して病理検査を行い、ピロリ菌の感染を確認します。ピンポイントで組織を採取するため、まれに菌がいない部位が採取されると、感染していても「陰性」と判定されることがあります(偽陰性)。
鏡検法
採取した組織をホルマリンに保存し、顕微鏡で菌の有無を確認します。
迅速ウレアーゼ試験
特殊な試薬で組織を染色し、色の変化により感染の有無を判定します。名前の通り、短時間で結果が分かるのが特徴です。
培養法
組織を培養してピロリ菌の有無を確認します。結果が出るまでに約1週間かかりますが、菌株の種類や抗生物質への感受性を調べられるため、より効果的な除菌治療を行う際に役立ちます。自費診療での詳細検査として活用されることがあります。
ピロリ菌の除菌治療
 ピロリ菌に感染していると診断された場合、除菌治療を行うことで胃炎や潰瘍、将来的な胃がんリスクを減らすことが可能です。治療は自宅で服薬するだけで済み、比較的短期間で完了します。除菌後には再検査を行い、成功したかを確認します。
ピロリ菌に感染していると診断された場合、除菌治療を行うことで胃炎や潰瘍、将来的な胃がんリスクを減らすことが可能です。治療は自宅で服薬するだけで済み、比較的短期間で完了します。除菌後には再検査を行い、成功したかを確認します。
一次除菌
抗生物質と胃酸分泌抑制薬を1週間ほど服用し、ピロリ菌の除去を目指します。
二次除菌(一次除菌が不成功の場合)
別の抗生物質を用いて再度除菌を行います。
ピロリ菌感染予防のポイント
ピロリ菌は主に幼少期に感染することが多いため、日常生活での感染予防は以下の点に注意することが推奨されます。
- 口移しで食べ物を与えない
- 生水や井戸水の飲用は避ける
- 家族に胃がんや胃潰瘍の既往がある場合は注意する
これらの対策に加えて、感染が疑われる場合は早めの検査・診断が重要です。













