- 機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia)とは
- 機能性ディスペプシアの原因について
- 機能性ディスペプシアの主な症状
- 機能性ディスペプシアの診断について
- 機能性ディスペプシアの治療と薬について
機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia)とは

「胃が重たい」「すぐに満腹になる」「食後に胃の中に物が残っている感じがする」「お腹が張る」「みぞおちが痛い」といった不快な胃の症状が続いているのに、胃カメラなどの検査では潰瘍や炎症、腫瘍といった明らかな異常が見つからない――このような状態は、機能性ディスペプシア(Functional
Dyspepsia:FD)である可能性があります。
かつてはこのような症状は「ストレス性胃炎」などと診断されることが多くありましたが、近年では胃そのものの構造には異常がなくても、胃の働き(運動や知覚)に問題があることで症状が出る疾患として理解されるようになっています。
「ディスペプシア(dyspepsia)」とは、胃もたれや消化不良などの総称です。機能性ディスペプシアは、こうした胃の不調が慢性的に続く病気であり、胃潰瘍や胃がんなどの器質的疾患が原因ではないという点が特徴です。
胃痛の原因が検査で特定できない場合、多くはこの機能性ディスペプシアによるものと考えられます。早めに消化器内科を受診し、正しい診断と適切な治療を受けることが大切です。
機能性ディスペプシアの原因について
私たちの胃は、食べ物が入ってくると上部の筋肉がゆるみ、食物を一時的に溜め込む働きをします。その後、消化が進むと胃の下部が収縮し、内容物を十二指腸へ送り出します。
機能性ディスペプシアは、こうした胃の運動機能に異常が生じたり、胃や腸の感覚が過敏になることによって起こる疾患です。
このような胃の機能は、自律神経によって調整されており、脳との連携が非常に密接です。そのため、ストレスや生活習慣の乱れ、暴飲暴食などが引き金となり、自律神経が乱れることで胃の働きが悪くなることがあります。
さらに、以下のような要因も機能性ディスペプシアの原因や悪化に関与します。
アルコールや喫煙:胃の粘膜を刺激し、運動機能や感覚を乱します
カフェインや香辛料:胃の知覚過敏を引き起こすことがあります
脂肪分の多い食事:胃酸の分泌が過剰になり、症状を悪化させる要因に
消化に時間のかかるタンパク質の摂りすぎ:胃もたれの原因となることがあります
ピロリ菌感染:感染がある場合、除菌により症状が改善するケースもあります
機能性ディスペプシアの主な症状
胃の不調を訴える方の多くが経験する以下のような症状が、機能性ディスペプシアによって起こることがあります:
すぐに満腹になる(早期飽満感)
胃の上部の「溜める力」が弱くなることで、少量の食事で満腹感を感じます。
食後の胃もたれ
胃から腸へ食べ物を送る機能が低下し、消化が進まずに胃に長く残ることで不快感が出ます。
みぞおちの痛み、胸やけ、げっぷ
胃や腸の知覚過敏があると、ちょっとした刺激でも痛みや不快感が生じます。
これらの症状が命に関わるような重大な病気であることは稀ですが、慢性的に続くことで生活の質(QOL)を大きく損なってしまうことがあります。日常生活に支障が出るような胃の不調を感じた場合は、我慢せずに早めに消化器内科を受診しましょう。
機能性ディスペプシアの診断について
胃の不快感や痛みといった症状は、胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの器質的な病変によっても生じるため、まずはこうした病気の可能性を除外することが重要です。
そのため、機能性ディスペプシアを診断するには「除外診断」が基本となります。
胃カメラ検査

まず行われるのが胃カメラ検査です。食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察し、炎症・潰瘍・腫瘍などがないかを確認します。必要があれば、組織の一部を採取して病理検査を行うことで、より正確な診断が可能になります。
当院では、内視鏡検査の経験豊富な医師が対応しており、経鼻内視鏡や鎮静剤を使用した検査も可能です。「つらい検査が不安」という方にも、できるだけ負担の少ない方法で検査を受けていただけます。
腹部超音波検査(エコー)
胃の不快症状の原因が、胃以外の臓器にある場合もあります。特に胆のう、肝臓、膵臓などは胃カメラでは直接確認できません。そこで、腹部エコー(超音波検査)を用いて、これらの臓器の状態を評価します。
その他の検査
症状や問診の内容に応じて、以下のような検査も行います。
血液検査
炎症反応や感染症、肝機能などの評価
レントゲン検査
腸閉塞や臓器の異常の有無を確認
便検査・ピロリ菌検査
感染症や胃の環境の調査
機能性ディスペプシアの診断は、器質的な疾患が否定されたうえで、症状の持続や経過を踏まえて総合的に判断されます。消化器に不調を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
機能性ディスペプシアの治療と薬について
機能性ディスペプシアの治療は、胃の働きを整えるアプローチと、胃酸の影響を抑える治療の2つを柱に進めていきます。さらに、日常生活の見直しも症状の改善に重要な役割を果たします。
生活習慣の見直し
治療の第一歩として、胃腸への負担を減らす生活習慣の改善が重要です。
糖分や脂肪分が多い食事、香辛料の強い料理などは胃を刺激しやすく、症状を悪化させることがあります。また、コーヒー・紅茶・アルコール・喫煙も胃の不快感を引き起こす要因となるため、できる限り控えることが推奨されます。
加えて、ストレスとの関係も深いため、リラックスできる時間を意識して作ることも大切です。規則正しい生活・十分な睡眠・適度な運動・趣味の時間の確保など、心と体のバランスを整える工夫をしましょう。
薬による治療
機能性ディスペプシアに対しては、症状に応じて以下のような薬が用いられます。
消化管の動きを整える薬
胃の動きを活性化させる薬として、アコチアミド(商品名:アコファイド)が使用されます。これは、食後の胃もたれや、少量でもすぐに満腹感を感じるといった症状の改善に効果が期待できます。
胃酸の影響を抑える薬
胃酸の分泌過剰による胸焼けや胃痛、げっぷなどの症状には、以下の薬が処方されることがあります。
- 胃酸中和薬
- H2ブロッカー(ヒスタミン受容体拮抗薬)
- プロトンポンプ阻害薬(PPI)
これらは、胃酸の分泌を抑えることにより粘膜への刺激を軽減し、知覚過敏による症状を和らげます。
漢方薬
体質や症状に合わせて、六君子湯(ろっくんしとう)や半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)などの漢方薬も有効です。特に、のどの違和感やストレス由来の症状に対して使われることがあります。
ピロリ菌の除菌治療
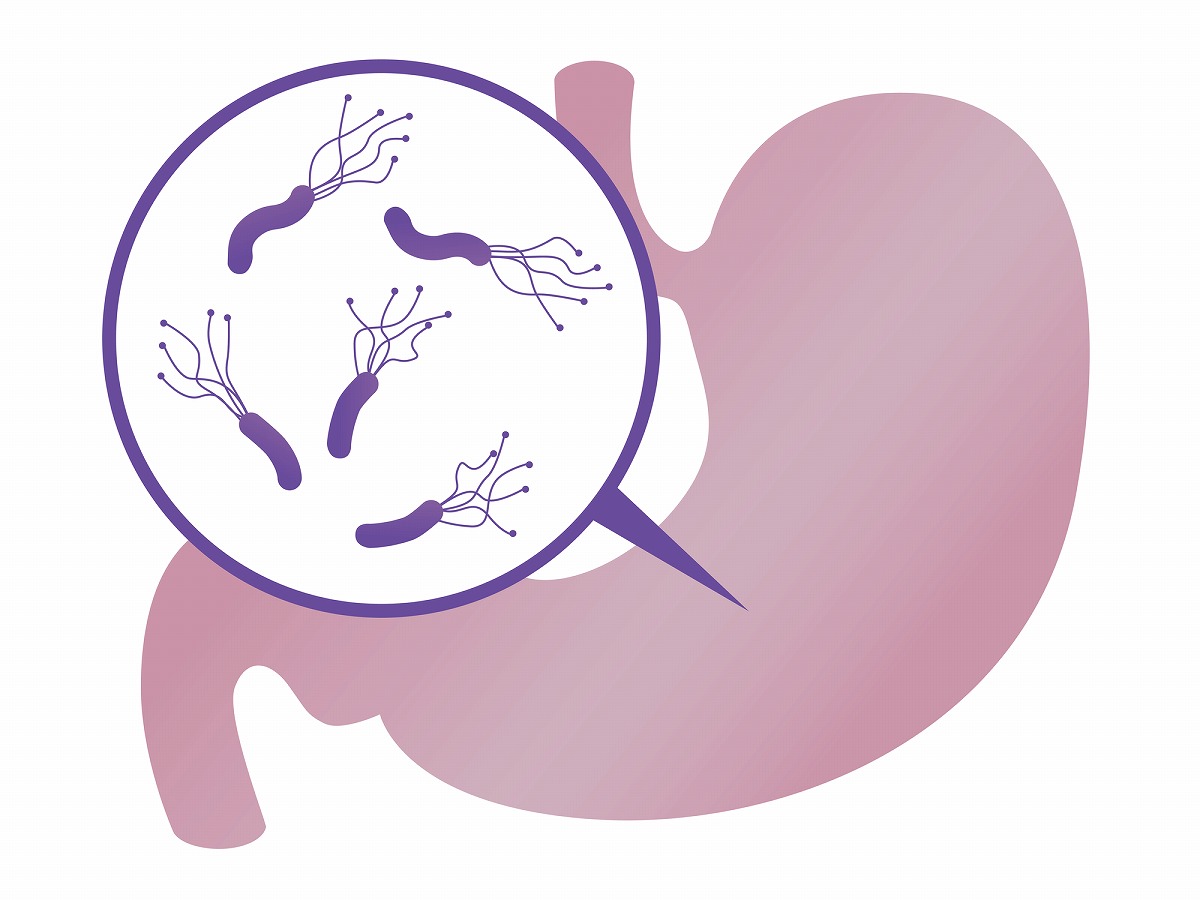
ピロリ菌が胃に存在する場合、これが胃の慢性的な炎症や不調を引き起こしている可能性もあります。ピロリ菌は、胃酸から身を守るためにアンモニアを発生させますが、これが胃の粘膜にダメージを与え続ける原因にもなります。
そのため、感染が確認された場合には、除菌治療を行うことで機能性ディスペプシアの症状が改善するケースがあります。













